【教職P】学外プラクティカムが始まりました
- 教教 わくわく倶楽部
- 2022年11月12日
- 読了時間: 2分
教教のドクター生は将来、大学の先生になって教員養成を充実させていける力を養うために教壇実習を行います。
11月8日、教育社会学研究室の佐々木龍平さん、11月11日に西洋教育史研究室の太田淳平さんがそれぞれの専門基礎の講義でプラクティカムを実施しました。


佐々木さんは、教育社会学の知見である、構築主義的アプローチについて、不登校が社会の中でどのように語られてきたのかを手がかりに講義しました。
不登校ひとつをとっても、昔は病弱や村の経済の問題として、ある時期から心の問題として、というように、時代ごとに非常に異なる捉え方がなされているのが、新聞や人々の語りから見えてきました。

終わったあとのホッとした姿。ニコニコしながらあぁーあそこでこうだったなぁ!と反省がつらつら始まりました。
太田さんは学校が社会の分断を埋めようとした歴史と作ってきた歴史について、日本とアメリカの事例を主に扱いながら講義しました。
「穢多・非人」と呼ばれた、社会的に差別を受けてきた人々に対して、日本の学校は「下々等学校」という、公教育よりも短くて簡素な内容しか教えなかったというそうです。学校が社会の差の構造を作ってきた歴史から、学校と社会の関係について理解を深めました。
二人は今回、大学の専門分野の「講義」を行いました。なので、90分間、学術的な内容を体系的かつ分かりやすく伝え、考えさせるための練習の場となりました。二人の授業とも、学生の手元のメモがぐんぐん進む、とても内容の濃い授業でした。
授業のディスカッションでも学生たちは与えられた資料をしっかり読み解き、理解を深めていました。
提示する資料の難しさ、与える課題のわかりやすさ、考えたくなるようなテーマ、学術的な深さなど、プラクティカムではさまざまな観点から授業を検討します。院生さんは二回目の教団実習で、ひやひやしながら、がんばってこの日を迎えました。
僕(助教)はすごいなぁと思いながら見ていましたが、指導教員にそれを伝えたら「あらそう?私は気になることがつらつらと・・・」とニコニコ厳しいことをおっしゃっていました。
広大院生さんは、ぴしぴし育っています。







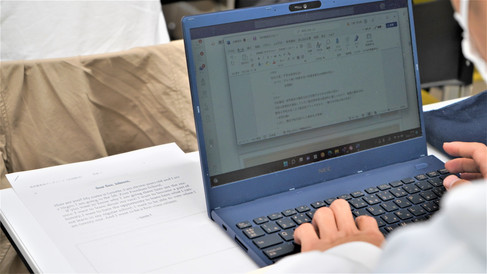




コメント