
教職P
履修生インタビュー

File 2.
自身の視野を拡張し、教育観を洗練する
安藤 和久(教育方法学研究室 2020年度入学)
広島大学の教職課程担当教員養成プログラム(以下、教職P)では「先生の先生になる」をスローガンに、教職科目のシラバス分析、シラバス作成、教壇実習、ポートフォリオ作成などを通して、教職課程を担当するために必要な力量形成を行っています。このプログラムでは教員養成を担うための教育力だけではなく、研究者としての研究力を含めてその力量を養成している点、それを教育学の他領域と横断した関��係の中で行っている点が面白い点です。今回はその研究室を超えた関係の中で学んだ経験を紹介します。
実習を通して見つめる自分
まずは教壇実習の際に実施される事前と事後の検討会の中での学びです。教職Pでは1コマの講義を学内で2回、学外で1回担当する教壇実習を行います。その際に指導計画に対する事前検討会と、実習の省察のための事後検討会を実施し、担当の指導教員含め、教職P受講生も参加して一��緒に議論を行います。どのようなことを身につけさせたいのか、そのためにどのような教材を準備するのか、といった教授方法に関する議論をはじめ、科目全体の中での担当コマの意味をどのように考えるのか、自身の研究関心とどのように連動するのか/させるのか、といった議論もなされます。なので、自ずから自身の研究に裏打ちされた教育観に向き合うこととなります。1回のコマを責任持って担当するという教育力に関わる養成と、担当回の内容を学問的にどのように理解しているのかという研究力に関わる養成がなされています。教育と研究の結合は教職Pで求められる学びだと実感しています。

共同研究を通して見識を広げる
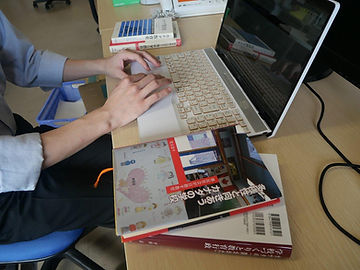
つぎに共同研究を通しての学びです。教職Pでは受講者の中で有志が集まって共同研究を行ないます。私は2020年度に「大学におけるオンライン授業の可能性と課題—学生と教壇実習を経験した大学院生へのインタビューを手がかりに—」と題し、5人での共同研究、共同研究発表を行いました。個人研究で取り扱っている研究対象やテーマから離れ、高等教育や教員養成の分野にチャレンジしたり、文献・史料読解が中心の研究方法ではなくインタビュー調査を実施したりなど、困難も多かったですが、それだけ自身の研究の幅を広げることができました。そして何よりも、研究を進めていく中でのディスカッションが自身の教育観や研究力の形成にとって重要であることを経験しました。自身の専門分野ではない教育哲学や教育行財政学、幼児教育学、西洋教育史を専門とするメンバーの指摘や構想から得る刺激は大きかったです。�教育の現状や課題を多様な学問領域から捉えることも、教職Pを通して養成されていると思います。